『都市』第105号・2025年6月
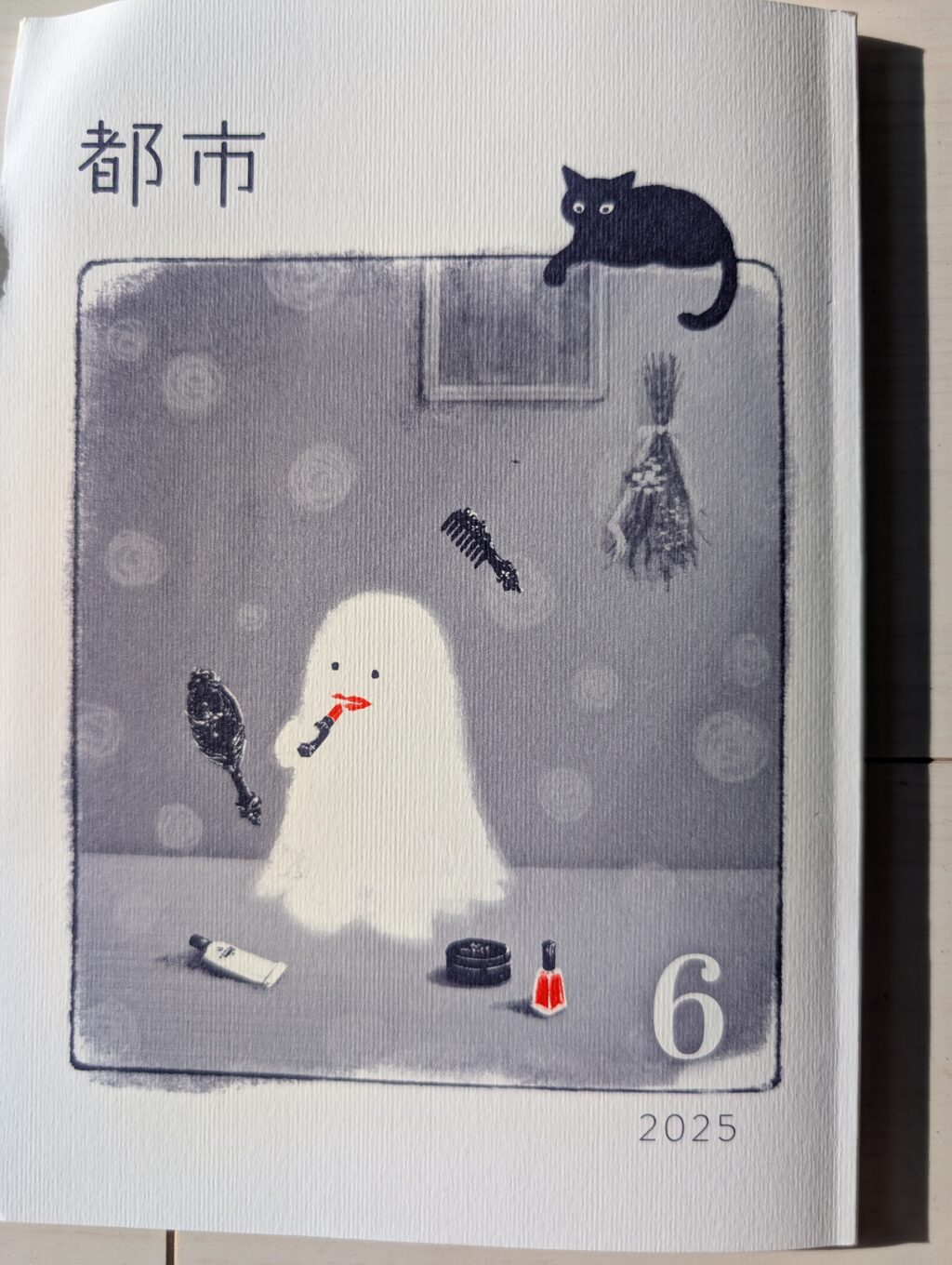
【青桐集】
料亭のマッチ使ひてどんど焚く
眼の手術終へてまさぐる水仙花
春雨や釣り人の肩動かずに
陽炎を突つ切つて行く消防車
弁当を使ふ最中や春の雪
【都市集】
靴底をしみじみと見て年暮るる
靴下ろしどこまでも行く春の空
火除地の雑草刈られ冬雲雀
春めくや用事をつくり乗る電車
ふと見ると探しゐるものうららけし
1996年に真打に昇進した直後から、それまで自らを律し戒めていたことのいくつかを解き放ちました。たとえば、大学卒業以来遠ざかっていたカトリック教会へと再び通い始め、明くる1997年の復活祭には洗礼を受けましたし、ほぼ時を同じくして以前から興味があった俳句の創作を始めました。
創作とはいささか大げさな物言いですが、それには訳がありまして、ぼくに何よりも欠落しているのは、詩心です。ですから、俳句を読んでも、その良さが分かるのはごく僅かでして、じっさいのところ名句を前にしても、この句のいったいどこがそんなに好いのだろうと、じつにしばしば悩むことになるのです。
鑑賞には不向きだと覚ったぼくは、一転、俳句らしきものをでっち上げることならばできるのではないかと、今から思えば不遜なる錯覚をおかし、俳句を学ぶために句会へと生まれて初めて参加したのでした。
宗匠は立教大文学部の先輩、須川洋子先生です。先生は巷間云われるところの人間探求派の一翼を担う、加藤楸邨門下らしく、人生万般にポジティヴな句風を旨とする方でして、それが何事につけネガティヴな俳風を好むぼくにはうまく作用したようで、どうやら未だに、続いております。
その須川宗匠主宰の『季刊芙蓉』に掲載された句を以下に転載します。原則として1号あたり8句前後掲句されます。(★)を付した句は、須川宗匠とその後継宗匠による特選句です。
須川先生の没後、慶應義塾の先輩である中西夕紀先生と出会い、先生が主宰する結社、「都市」俳句会に参加し、現在に至っています。
中西夕紀主宰は、藤田湘子の門下で、2008年に「都市」を創刊しました。
『必携季寄せ』(角川書店、2003年)には、先生の下記の句が採られています。
一客一亭屋根替もをはりけり
闘鶏の赤き蹴爪の跳びにけり
空仰ぎ弁当使ふ四迷の忌
戸を開けて月の近さや氷頭鱠
貝焼の貝の中へも飛雪かな
何もかも丸く刈られし御命講
寒鮒にはつかな泥のたちにけり
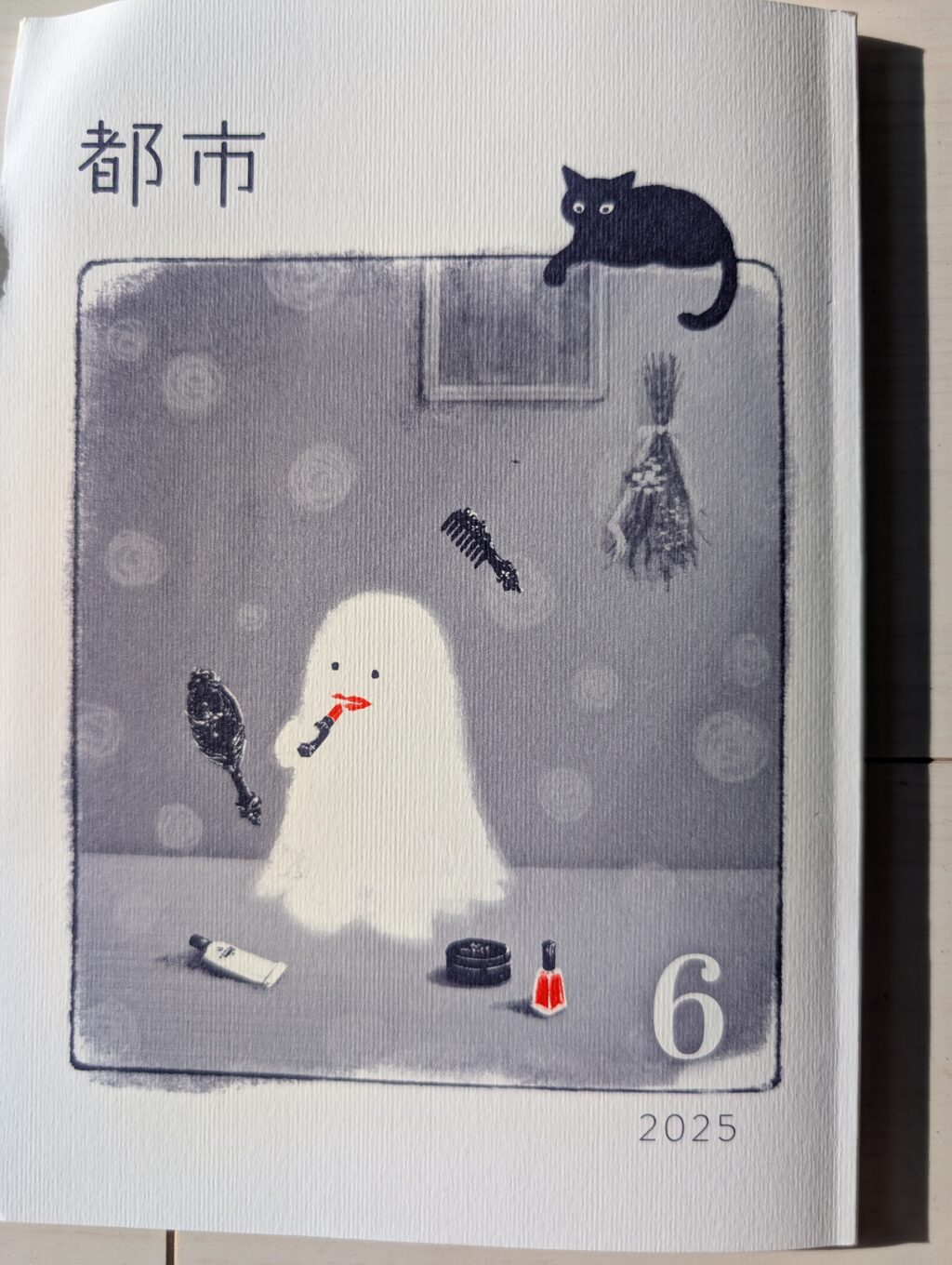
【青桐集】
料亭のマッチ使ひてどんど焚く
眼の手術終へてまさぐる水仙花
春雨や釣り人の肩動かずに
陽炎を突つ切つて行く消防車
弁当を使ふ最中や春の雪
【都市集】
靴底をしみじみと見て年暮るる
靴下ろしどこまでも行く春の空
火除地の雑草刈られ冬雲雀
春めくや用事をつくり乗る電車
ふと見ると探しゐるものうららけし
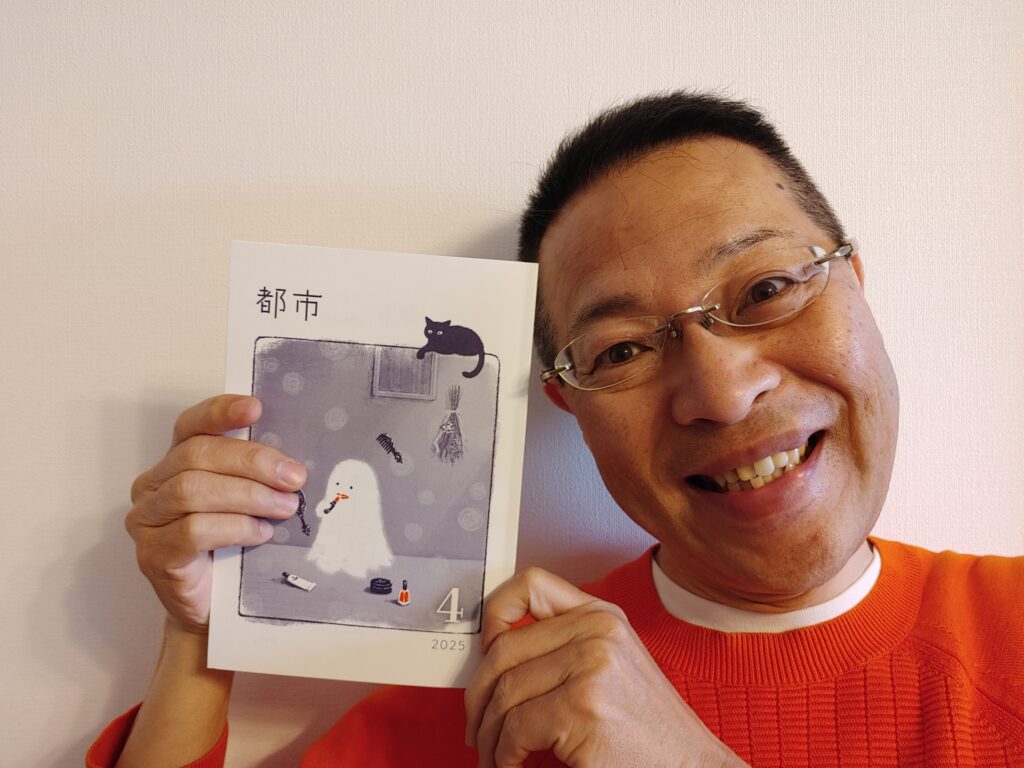
【青桐集】
稽古終へ子どもも犬も息白し
いつの間に正座にて読む漱石忌
綿虫に誘はれ髪を切りに行く
宮崎斗士(海原)評:綿虫のふわり感と「髪を切りに行く」
との配合の妙。「誘はれ」が佳い。
蔦枯るる学び舎を背に撮る写真
目玉焼黄身を開きて冬ぬくし
【都市集】
福耳の看護師に照る大夕焼
喧嘩して仲直りせず霜の声
風邪引きて鬼のごとくに服薬す
刹那だけ信じて眠るクリスマス
ささくれを気にしながらの山始
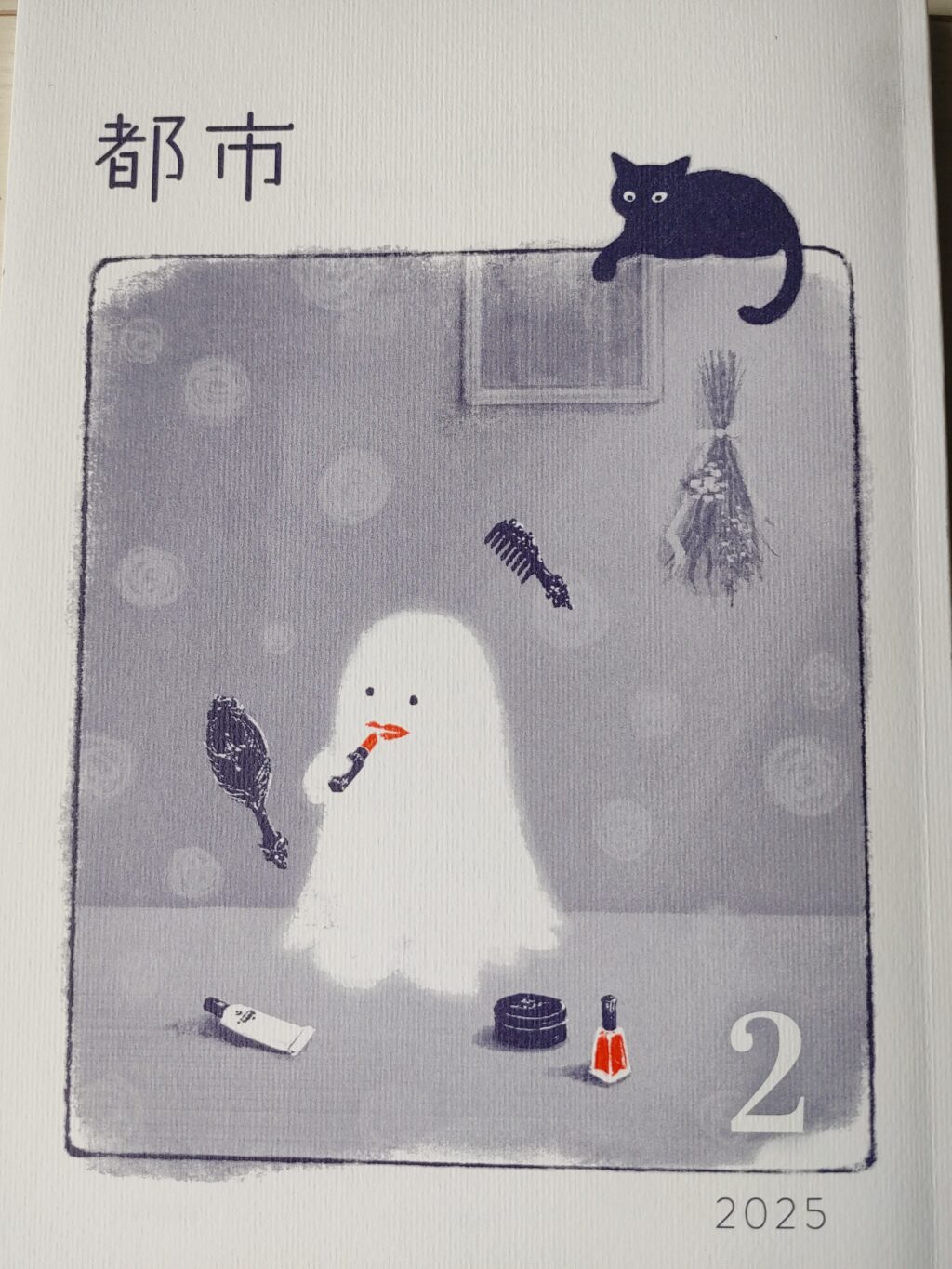
【青桐集】
広辞苑引かぬ日はなしとろろ汁
秋暑し帽子被りて乗る筏
母を呼びともに見つむる小望月
火事跡にいつまでもある三面鏡
手を合わせ時の伸びけり墓参り
【都市集】
月明に宛名確かめ投函す≪都市の窓≫
濯ぎ物きれいにたたみ秋麗
神輿から即かず離れず追ふ子ども
小夜時雨床から出でて米を研ぐ
拍手をはつきり打ちて冬うらら
目貼して思ひのままに高笑ひ
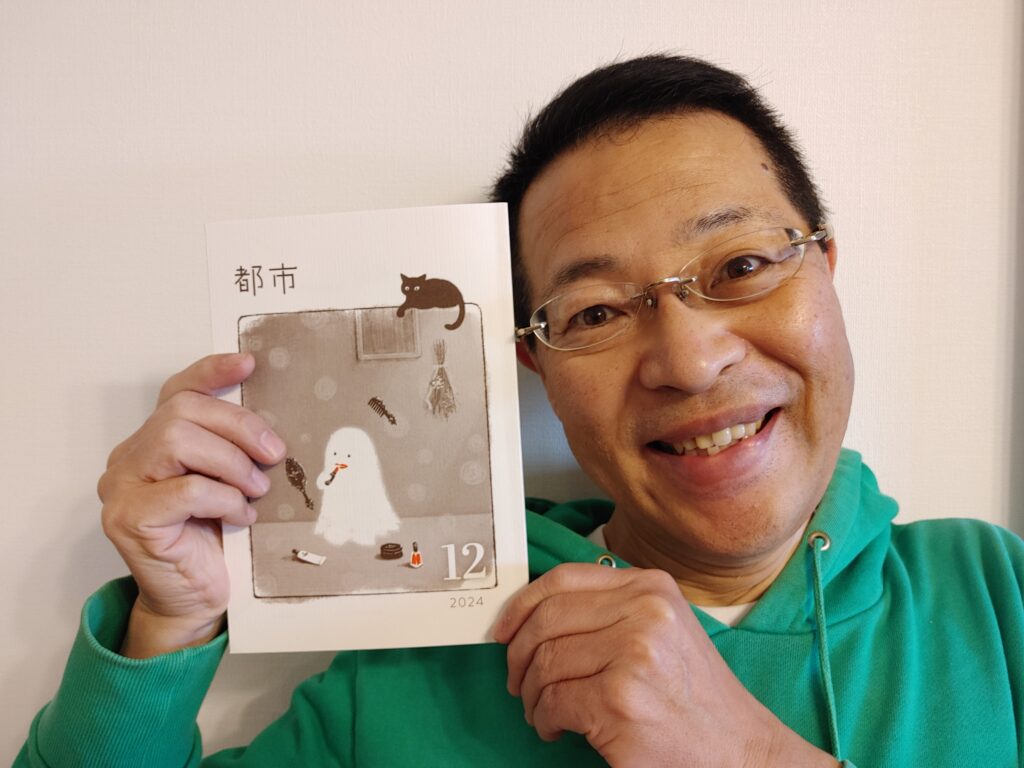
【青桐集】
夏木立出できしときは別人に
主宰寸評:気持のよい夏の木立を
歩いて来て、すっかりリフレッシュ
したのだろうか。このように別人
になれたら、本当にいいのだが。
恋破れ青きトマトにかぶりつく
強烈に口開けて寝る熱帯夜
夫婦仲良過ぎてすする冷し麦
秒針の時刻む音三尺寝
【都市集】
傘を買ひカントも買ひて梅雨に入る
平澤ひなこ評:リズムよく、外出して読書もしてと準備
怠り無い作者が面白い。
子が親の日傘を持ちて見る試合
いつまでも見送る人に大夕焼
月天心写真を撮りてまた見上ぐ
マジシャンがショーの仕込みの熱帯夜
【青桐集】
風薫る休講掲示肩越しに
腕時計重く感ずる梅雨の入
雲海の中より聞こえ巡礼歌
手招かれ友と見入るや水馬
道炎ゆる幾たびも遭ふ救急車
【都市集】
夏期講習いつもより水多く飲む
読む本の余りに多し夏休み
たしかめて何度も見遣る余り苗
鮎の頭食らひて笑みの女の子
蜜豆の赤豌豆から掬ふ子よ
「都市集」巻頭百句
春の昼離れ見詰むる紙芝居
【青桐集】
競漕の光の中を突き進む
長き会議いまだ終はらず春の虹
師と呼べる人を数へて春の風
無くなりし腕時計出づ五月晴
足袋に趣向凝らして臨む大茶会
【都市集】
歌ひつつ帰る幼の復活祭
読みかけの頁めくるは若葉風
若葉風悪夢を払ひ吹き抜くる
印鑑を忘れ戻りて春時雨
のどかさや万葉集を読みふけり
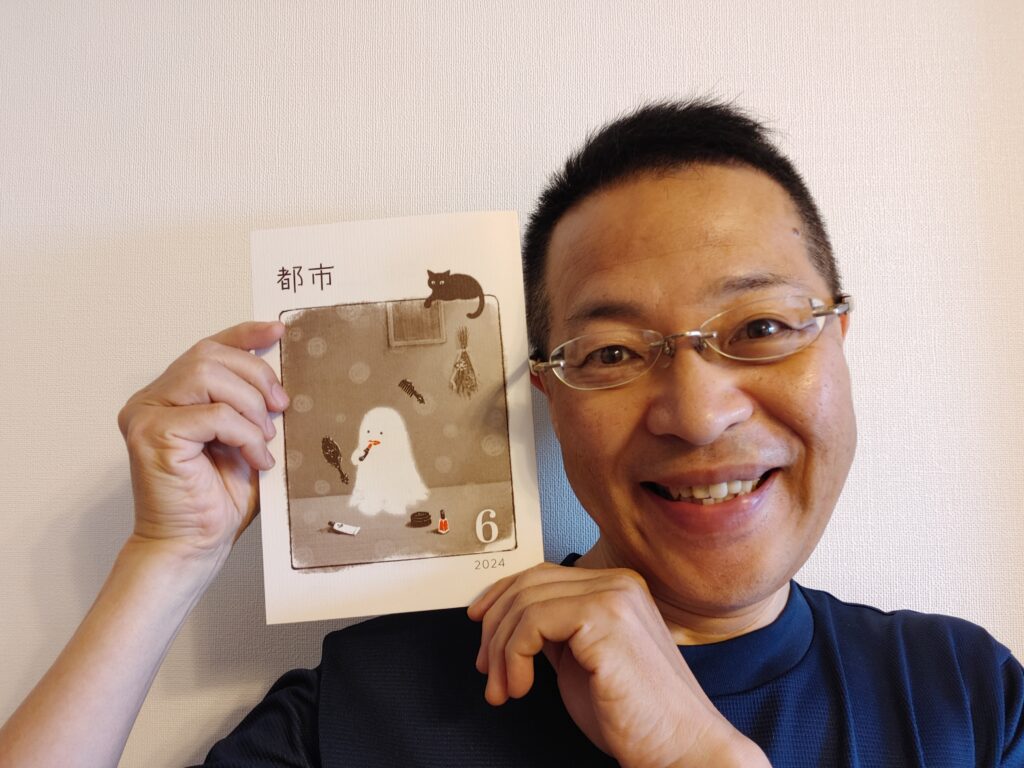
【青桐集】
ほめらるる夢から覚めて春の昼
本読みて乗り過ごしけり初電車
犬抱きて焚火の輪から去りかねる
春浅し手品の稽古いつまでも
残る雪歌の続きを思ひ出す
【都市集】
初相場途中で拾ふ五圓玉
いつもより大きく背伸び年始酒
木の芽雨おかげさまにてひと眠り
春燈に爪切る人の影の濃く
欄干に落とし物かけ春の昼
春の燭逢瀬の靴を磨きけり
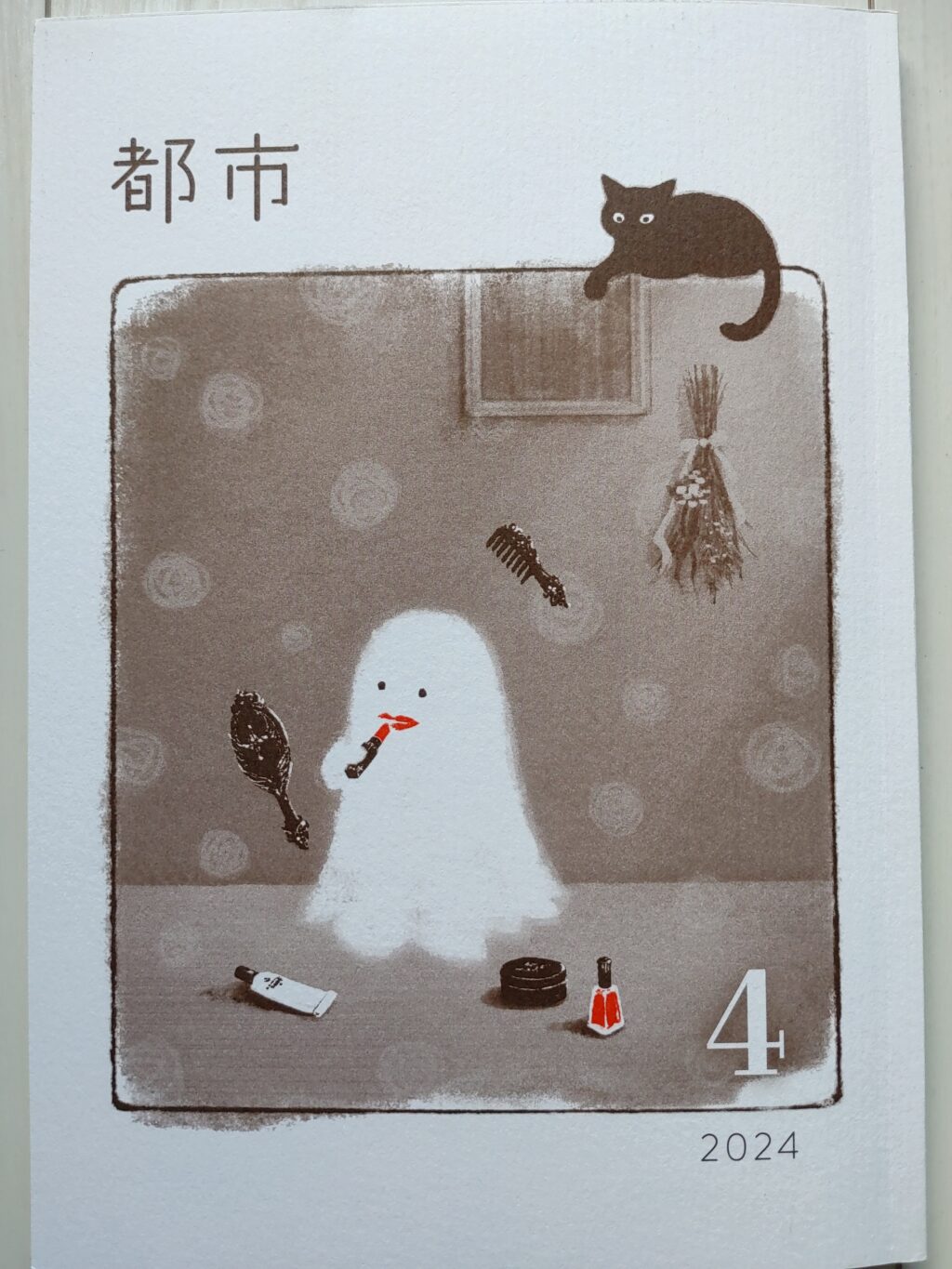
【青桐集】
梯子乗り一点見つめ昇りをり
障子に映る我が身を攻める仔犬かな
パラフィン紙粉粉となる憂国忌
図書館の行きも帰りも枇杷の花
昨年の続きを開けて読始
黒岩 徳将(いつき組・街)
スマートフォンのアプリを使えば、
前回読んだ箇所を的確に示してくれ
るのだが、この句は紙の本と解釈し
た方が本の手触りを感じるし、栞が
あるかもしれないなどと想像の余地
が膨らむだろう。新年の清々しい気
分を寿ぐように詠むのではなく、年
が変わっても淡々と本を読み進めて
いく主人公の平静ぶりを楽しみたい。
考えられる日時は様々だが、いっそ
のこと元日の深夜につい先ほど中断
していた読書を再開するという句な
らなお面白いと思う。
【都市集】
友引に寄席開く寺夜鷹蕎麦
眼を休め遠くを見るや帰り花
熱燗や御礼の声は高らかに
首にざぼん提げて来たれる松葉杖
帽子脱ぐ間もあらばこそおでん酒
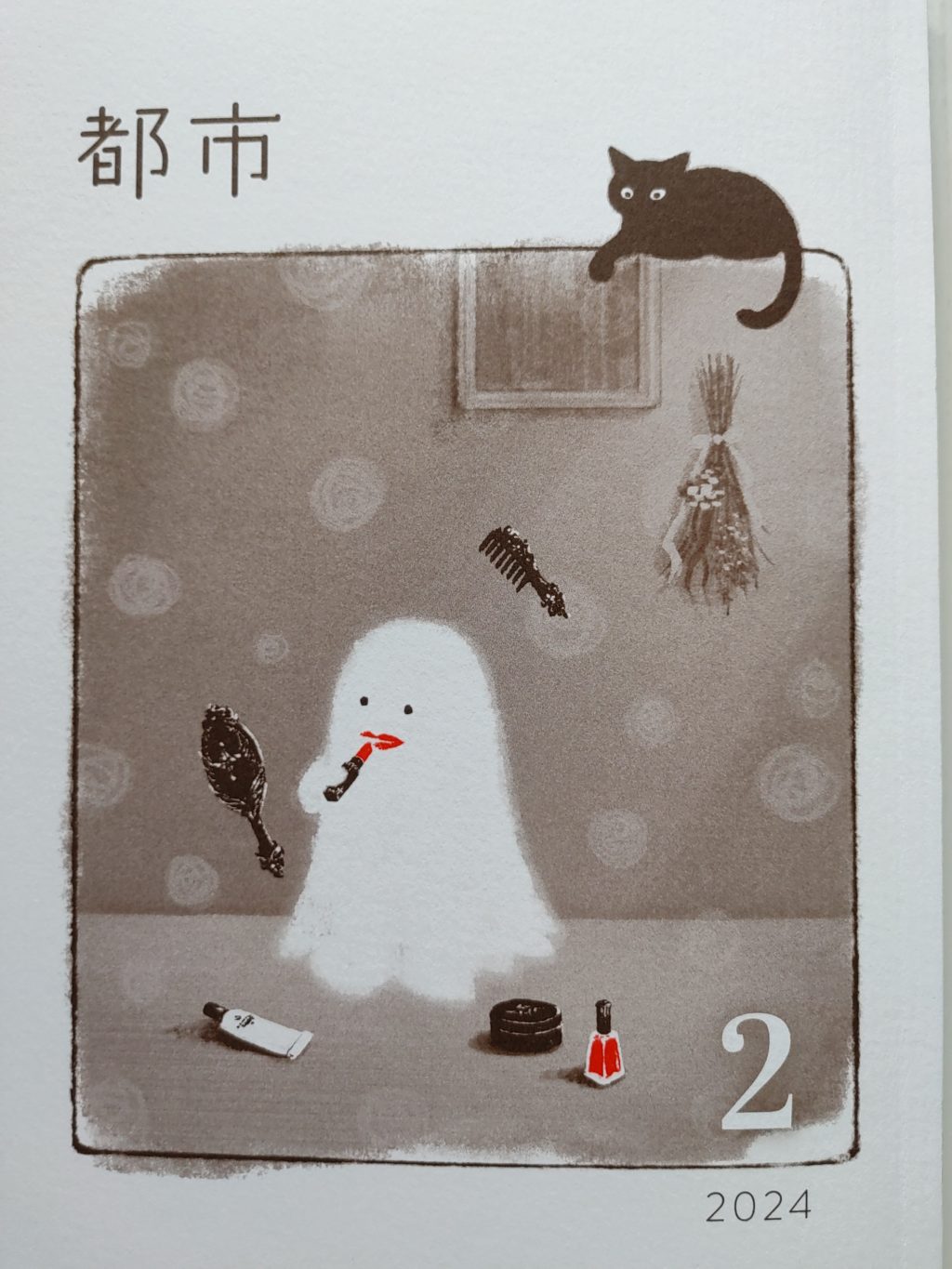
【青桐集】
結局は同じセーター選ぶ父
主宰寸評: 父へのプレゼントのようだ。
一緒にデパートへ行って欲しいものを物色
していた父が選んだのは、すでに持ってい
るセーターと同じものだった。何事にも意欲
のなくなってしまった、老いた父を愛おしく
思ったことだろう。
無患子を見つつかすかな風を知る
キャッチボールやめて見上ぐる雁の列
気ぶつせいな茶会を終へて秋の雨
澄める秋心字池にて落ち合へり
【都市集】
冬ぬくし久方ぶりの今治水
いつの間にむきになりけり掃納
酉の市一円玉を拾ひ上げ
泣く子ども天の川見て笑みこぼす
渋き茶を飲みつ聞こゆる法師蝉
【青桐集】
山開きいつもの顔を探しけり
夕顔を見つめし後に書く手紙
夜店にて首から提げし財布出す
検眼の最中聞こゆる秋の蝉
秋めくや列の途切れぬ洋食屋
【都市集】
胡瓜もみ迷ひながらも酢を飲みて
岩魚釣大漁にても隠す笑み
黒眼鏡はづしたたんで墓参
松葉杖ついたまま見る木槿かな
結び瘤ほどきあぐねて夏の果
町田市議会議員 会派「自由民主党」/(一社)落語協会 真打


 042-720-4644(留守電対応)
042-720-4644(留守電対応) 042-720-4644
042-720-4644