7月14日岩手県奥州市、7月15日宮城県大崎市、7月16日埼玉県戸田市
【奥州市議会】7月14日
1、議長の所信表明(令和4年3月)
議長就任希望者の所信表明は議場でおこなうようになった。
それは、市民への約束の表明を意味する。また、それを議長マニフェストにまとめ、工程表も公表した。
(1)議長マニフェストⅠ奥州市議会の「見える化」の推進に努める
1)実行計画による実行目標と工程の明確化
2)各委員会の活動状況等の見える化
3)議会改革の取組状況とアウトカムの評価・公表
4)議会ICT推進方針の明確化
(2)議長マニフェストⅡ広報・広聴の充実・強化を図る
1)広報と広聴機能の一体的な取組体制の整備
2)様々な世代の市民参画と多様な市民意見の把握
3)広報の工夫と充実を図り市民に分かりやすい情報発信
(3)政策立案・政策提言サイクルの充実・強化を図る
1)決算・予算審査の連動による政策提言サイクルの構築
2)広聴活動で把握した市民意見を反映させる仕組みづくり
3)各常任委員会の継続した政策提言の実施とフォローアップ
(4)議員間討議の制度化による十分な審議と市民への説明責任に努める
1)対話をベースにした議員間討議の制度化
2)重要課題等の十分な審議と合意形成、結論に至る経過の明確化
(5)議員の成り手不足解消に向けた調査研究と対策の実施、主権者教育の推進に努める
1)議員の成り手不足解消に向けた調査研究と対策の実施
2)議員定数及び議員報酬の在り方の調査研究
3)小中高生・若者・女性との模擬議会、ワールドカフェや議場・議会見学会の実施と主権者教育の推進
2、情報のバタフライ・エフェクト

(1)新たな情報戦略の展開(平成29年7月)
1)タブレット端末の導入とペーパーレス化
2)facebook・twitter(現:x)の開始
3)FM放送『電波に乗せて!奥州市議会』の開始
(2)情報戦略の多角化(平成30年6月~)
1)議案・全員協議会・政務活動費資料の完全公開
2)タブレット・スマホ対応の議場放送開始
3)『市議会だより』のリニューアル
4)instagramの開始
(3)コロナ禍の情報展開(令和2年3月~)
1)タブレット端末でのオンライン会議・調査・視察の実施
2)line worksによる連絡手段を新設
3)コロナ対応の『議会BCP』の策定
4)googleフォームを活用した政策提言のためのオンラインアンケートの実施
(4)業務継続の研究と実践(令和2年6月~)
1)議会BCPの研究・策定
2)業務継続の実践
(5)line worksの導入(令和2年3月~)
1)line worksはLINEのビジネス版アプリ
2)SNSだから災害にも強く写真添付で被災報告にも使える
(6)ライブ字幕システムの導入(令和5年8月~)
1)インターネット中継では画面の下にライブ字幕を表示できる
(7)zoomでの本会議に対応(令和5年8月~)
1)議場をオンライン対応にするため、zoom表示可能に改修した
(8)会議録の電子化に対応(令和5年10月~)
1)地方自治法第123条に規定する会議録の電磁的記録化・電子署名に全国で初めて対応
(9)電子署名の活用(令和6年4月~)
令和6年4月、地方自治法の改正により可能となった請願のオンライン受付を開始
(10)ICT推進方針の策定(令和5年8月~)
1)推進事項・設備の基本事項を規定した
(11)AI生成画像活用の紹介
1)市議会だよりに生成画像を活用(令和6年4月~)
(12)議員間討議のガイドラインの策定(令和5年8月)
1)対話⇒議論⇒討論⇒議決(決断・成果)までのプロセスと地印鑑討議と位置づける。
3、新たに巻き起こったゆらぎ~政策提言~
(1)前議長・副議長の所信表明(平成30年3月)
前議長、積極的な情報開示と市民の声を拾い上げる広聴活動
前副議長、市民懇話会の充実による幅広い世代の民意把握と市政への反映
(2)政策決議提案
政策立案等ガイドライン(令和元年5月)
政策決議提案、政策提言、政策立案
(3)実現した施策の紹介Ⅰ~令和元年政策決議提案
1)自家用有償旅客運送の導入(令和2年10月)
(4)実現した施策の紹介Ⅱ~令和3年政策決議提案
1)地域おこし協力隊の戦略的募集(令和4年12月)
(5)生成AI活用の紹介~令和5年政策決議提案
1)ChatGPTで対話・議論補助(令和5年6月)
大リーグ大谷翔平選手の地元奥州市議会は、「チェック」と「提言」による「二刀流議会」で市民の負託に応えることを標榜しています。
【大崎市議会】7月15日
1、議会改革の取組(概要)
大崎市議会では、平成24年9月に「大崎市議会基本条例」を制定し、本条例の目的の実現(市民に開かれた議会・市民参加を推進する議会など)を目指し、議会改革に取り組んでいる。
この条例は、1.議会機能の強化、2.市民参加の機会拡充、3.市民への情報発信をうたっている。
そこに、正副議長の所信表明が項目としてあり、その内容は、所信表明の全員協議会でのインターネット配信である。
2、議長選の所信表明
(1)正副議長の所信表明を演説するために必要な事項については、「大崎市議会正副議長選挙立候補における所信表明演説の取り扱いについて」の中で定められている。この取り扱いは、平成26年の会派代表者会議で決定されている。
1)所信表明の演説
選挙に先立ち、会議の休憩中に議員全員協議会を開催して実施。
・所信表明は、本会議場で実施
・所信表明は公開するものとし、あわせてインターネット中継を行う。
・所信表明は口頭で行うものとし、発言時間は立候補者1名につき10分以内とする。
・所信表明の順序は、所信表明届出書の届出順とする。
3、議会基本条例(制定)
1)①検討組織:議会改革特別委員会(平成22年6月~平成25年9月、3年3か月、委員会54回開催)
②構成議員:18人
③設置目的:地方分権改革の進展や市民の議会に対する関心が高まっている中にあって、地方自治体を取り巻く情勢に幅広く対応し、市民の負託にこたえることを目指した議会の活性化を図る。
④主な検討項目:ア議会機能の充実に関する事項(19項目)、イ 広報広聴活動に関する事項(8項目)、ウ 議会基本条例、エ 議員定数と議員報酬
2)基本条例の制定
条例の特徴(基本条例第1条:目的)
①この条例は、議会及び議員の活動原則を定め、市政における唯一の議決機関としての議会の役割を明らかにするとともに、議会の最高規範を定めることにより、地方自治の本旨に基づき、市民福祉の向上及び市政の発展に寄与することを目的とする。
制定後の変化:すべての議会・議員活動は、基本条例に基づき実施している。
4、議会基本条例の検証
1)①検討組織:議会改革推進協議会(会議規則で定める「協議等の場」)
②構成議員:全議員 ※幹事会:正副議長、各会派等から1名
③検証実施に至る経緯
【令和3年の検証】
議会基本条例は、議会及び議員の活動原則であることから、条例の目的達成度や条例の見直しについて検証し、評価を実施した。
【令和5年の再検証】
前回の評価においては、各条文の目的達成に必要な具体の取組まで協議していなかった。また、令和4年の議員選挙において、1期生7人が誕生しました。この条例は議会における最高規範であり、条例の趣旨を理解するためにも、議員改選後の新体制において、再検証・評価を実施した。
④検証方法:基本条例全22条の「段階評価」、「管理評価」を実施
5、高校生との意見交換会
1)実施対象:大崎市内の各高校生に在学する生徒
2)目的:次代を担う若者が市政への理解と関心を高め、市行政及び議会を身近な存在として興味を持ってもらうとともに、選挙権年齢の18歳への引き下げによる若者の政治参加の意識醸成を図る。また、子どもたちが地域の一員として主体的に考え、地域の魅力を感じ郷土愛を育んでいくとともに、高校生の意見を聞く機会を設けることで若者の意見や考えを把握し、議会の充実強化につなげることを目的として開催する。
4)議会出席者:全議員
5)テーマ:「大崎市の魅力を高める地域活性化」高校生がテーマを決定
6、大学生との意見交換会
1)目的:若年投票率の向上を目的に活動する「NPO法人ドットジェイピー宮城支部」からの申し出を受け、次代を担う若者が市政への理解と関心を高め、市行政及び議会を身近な存在として興味を持ってもらうともに、大学生の意見を聴く機会を設けることで若者の意見や考えを把握し、議会の充実強化につなげることを目的として、令和3年3月及び12月に開催した。
2)意見交換の進め方
①議会のしくみについて:資料に基づき議員が説明する
②一般質問:事前通告に基づき、座長の指名を受けた学生が一括で質問し、議員が答弁する。その後議員の答弁に対し、質問した学生が再質問する。
③意見交換:学生が地域活性化や市政に関するテーマに沿った意見発表を行い、その後、議員と学生が意見や感想を述べあう。
7、議会報告・意見交換会
1)事業実績
①主管:議会運営委員会
②実施対象:市民(中学校区11地区で12会場で実施)
③実施時間:平日午後7時~午後8時30分(会場他により平日日中開催)
④テーマ:要望会とならないようにするため、対象ごとに設定
・市民対象⇒市政課題(会派⇒議運で協議・設定)
・団体対象⇒各常任委員会で現状の市政課題を基に団体選定し、テーマ決定
2)「議会報告・意見交換会」の現状・課題
現状:参加者の固定化、初めての方が発言しにくい、市への要望、市民意見は報告にとどまる
課題:幅広い年代層の参加者の確保、発言しやすい環境、一般質問や会派代表者で活用⇒議会としての政策提言(市民福祉の向上)
【戸田市議会】7月16日
1、議会改革の推進体制
1)議会改革特別委員会が中心
構成:定数9名+議長 ※すべての会派(7会派)が参加
特徴:原則全会一致
2、議長選挙に係る所信表明会について
(1)導入の経緯
議会改革の取組のひとつとして導入した。
議長に立候補した候補者が、議会として取り組んでいきたいことを表明する機会を設け、表明することで、議会改革の進展と、市民の議会に対する関心を高める効果が期待できる。
そこで、議会改革特別委員会における協議を重ね、偽証の所信表明会を先行して導入している議会の取り組みなどを参考とした。
その結果、平成22年12月に「戸田市議会議長選挙に係る所信表明会実施要領」を制定。
1)議長の所信表明会開催に当たっての決定事項
・所信表明は、議長選挙が行われる議会の開議までに議場において行う。
・所信表明会の進行は、議長選挙の所信表明者以外の年長の議員が行う。
・所信表明の持ち時間は、1人当たり10分の範囲内となっており、演壇で行う。
・所信表明に対する質疑は行わない。
・所信表明会は公開で行うものとし、ライブ中継や録画放送する。
・執行部の出席は求めない。
・議長の所信表明を行った者以外への投票を妨げない。
3、議会におけるICTの活用について
1)タブレット
①iPad Air Wi-Fi Cullularモデル
②画面サイズ 13インチ
③容量 128GB
④Apple Pencil Pro
⑤マグネットキーボードケース
2)グループウエアソフト
これまでの連絡手段は、電話・メールだったが、日程調整等、多人数で調整を要する機会が多い。
また、災害時等緊急事態の際は、戸田市議会BCP(業務継続計画)に基づき、戸田市議会災害対策支援本部を設置し、被害情報の集約等を行うため、より迅速な情報共有を行う必要がある。
そこで、令和6年8月からline worksを導入した
このことにより、平時でのコミュニケーションがより円滑になり、災害時での情報共有も効率化した。
3)オンライン委員会
①会議規則等の改正
・完全オンラインだけでなく、一部の委員のみがオンラインで参加するハイブリッド型も可とする。
・災害時に限らず、公務、疾病、看護、配偶者の出産補助、育児、忌引き、その他やむを得ない事由の場合でもオンライン出席可
・委員のほかにも、執行部、公述人、参考人もオンライン出席可
②月イチオンラインミーティング
いざという時にスムーズに開催できるよう、日頃からオンライン会議に慣れる機会を創出。
・全議員を対象とした「月イチオンラインミーティング」を毎月開催
・定例会前の議案等事前説明会をオンラインで開催
4)セムカン
①政務活動費管理システム「セムカン」の実証実験について
(1)主なメリット(職員)
情報公開に向けて、マスキング用の印刷やPDF化などの処理が不要
(2)主なメリット(議員・事務局双方)
各会派の政務活動費の用途が一目で分かり、情報公開の質が向上する
5)議会だよりの編集
①Acrobatを使用した校正作業
(1)作業期間は1週間程度
【メリット】
・広報委員及び事務局で情報共有できる。
・広報委員会前に各々が校正作業を行えるため、委員会時間の短縮につながる
・紙の削減につながる
4、議会モニター制度について
1)導入の経緯
戸田市議会では、議会改革特別委員会において、平成21年に「市民への情報提供・市民との意見交換」について協議を進め、開かれた議会に向けての方策を検討した際に、『議会報告会』の実施について検討を行った。
【検討結果】
・市域が約18平方キロメートルと狭く、傍聴を希望する方が比較的容易に傍聴できる環境にある。
・議会への関心が低い状況での議会報告会の実施は、時期尚早である。
これらの結果、議会報告会の実施は見送ることとなり、議会報告会に代わる形で平成23年4月に『議会モニター制度』を導入した。
2)目的
議会モニターを設置することにより、戸田市議会の運営等に関し、市民からの要望、提言その他の意見を広く聴取し、市議会の円滑かつ民主的な運営を推進することを目的とする。
3)議会モニターの職務(要綱第3条)
(1)会議を傍聴し、会議の運営に関する意見を提出する
(2)「とだ議会だより」及び市議会ホームページに関する意見を提出する
(3)議長が依頼した市議会の運営に関する調査事項に回答する
(4)市議会議員と1年に1回以上、意見交換を行う
(5)議会に関する情報発信をすること(令和6年10月22日改正)
(6)その他議長が必要と認めた職務

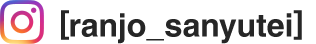

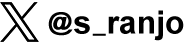

 Facebook [3ranjo]
Facebook [3ranjo] X(旧Twitter) @s_ranjo
X(旧Twitter) @s_ranjo Instagram
Instagram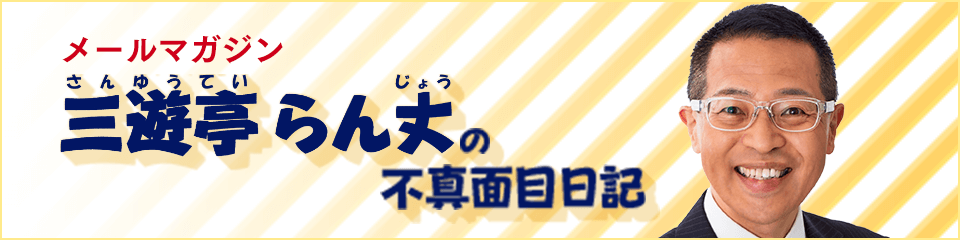


 042-720-4644(留守電対応)
042-720-4644(留守電対応) 042-720-4644
042-720-4644